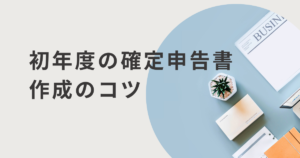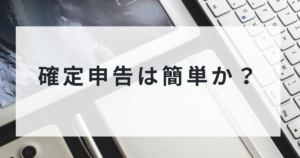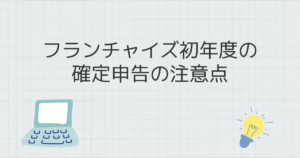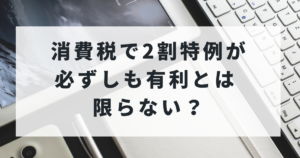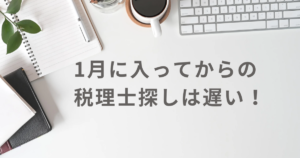先日、面識のない税理士から一通の手紙が送られてきました。税理士事務所を譲る相手を探しているという内容でした。譲る条件は後述しますが、色々考えさせられる内容でした。今回は税理士事務所の引継ぎについて書こうと思います。(もちろん、その方から譲り受けることはありませんが)
知らない80歳の税理士から手紙が来た
手紙を送ってこられた税理士の名前を日税連の税理士検索で検索すると、80歳の税理士からの手紙だということが分かりました。
おそらく近畿税理士会の会報に載っている新規登録者へ一斉に手紙を送っているのだと思います。
手紙の内容はこんな感じでした。(wordで印刷、手書きではありません)
- 居抜きのような感じで備品はそのまま使ってもいい
- 顧問先の紹介も出来るが、職員とパートも引き続き雇って欲しい
- 事務所は借入をしてでもいい立地条件の場所に借りたほうが成功しますよ(この事務所は立地が良いので、成功したければ、この事務所を引き受けてくださいという意味だと思います)
備品は確かにそのまま使えるのは、初期投資代が浮いて良いかもしれません。
顧問先と職員はセットのようです。セットとは一言も書いていませんが、顧問先が欲しければ、今の事務所をそのままの状態(職員を継続して雇用する)で引き継いで欲しいのだと思います。
なぜ80歳になるまで事業承継をしなかったのか?
前のブロックでも書きましたが、この税理士の方は80歳です。
税理士の平均年齢は60代なので、80代の税理士も一定数はいると思います。
しかし、80歳の税理士が代表者として事務所所長をしているのは、大変失礼ながら如何なものかと思います。
確かにご高齢の税理士の先生も多数おられますが、その殆どが実務の第一線からは退き、長年の経験を活かしたアドバイスをする相談役の様な立場の先生だと思います。
租税法の第一人者である金子宏先生も御年90歳のようですが、学者の先生達はさて置き、実務家として年齢を考えた場合、80歳という年齢では実務をこなすことは難しいように思えます。
「税理士登録情報の研修時間ゼロ時間」というのが、それを如実に物語っていると思います。Webで見て受講する研修を受けることができないということは、パソコン自体を扱えないのだと思います。Wordの手紙は職員かパートの方が代わりに作成したのだと思われます。
もちろん、職員の方(年齢や税理士試験の科目合格数などは不明)が事務所を継ぐ予定で事業承継を考えていたのかもしれませんが、結果として事業承継の問題が解決されていません。
では、何故80歳になるまで後継者問題が解決していないのでしょうか?
税理士事務所の事業承継には、他の事業承継と異なる特殊な事情があります。
税理士資格がないと税理士事務所を引き継げない
特殊な事情とは、ご承知の通り、引継ぎする人に税理士資格が必要だということです。
個人商店や一般会社でも代表者になるためには、それなりの経験や資格が必要ですが、引き継ぎたいと思えば、引き継げます。
一方税理士事務所は、税理士資格を取るのが大変難しいです。
この手紙を出した税理士事務所の職員も、何らかの事情で税理士資格を取れなかったのだと思います。資格さえ取れていれば、こんな手紙を送らずに済んだはずです。所長税理士も80歳になるまで代表税理士として頑張る必要はなかったはずです。
正確なデータが取れませんが、私が聞いた話では、税理士試験を目指すために専門学校に通い始めて、実際に税理士資格を取得できた人は、たった3%だそうです。
税理士事務所を引き継ぎたくても引き渡しできない所長税理士、引き継ぎたくても引き継ぎできない事務所職員が世の中には沢山います。厳しいですが、これが税理士事務所業界の現状です。
今回、何故こんな話を書いたかというと、私自身がつい1年前までその状態だったからです。
今は税理士資格を持っていますので、事務所を引き継ぎできますが、この手紙を送られた先生の話は決して他人事には思えないのです。
私の知り合いにも今回の様に、後継者(引継ぐことを予定している人)が税理士資格を取れていないという人がいます。また、後継者とすることを予定していた人が税理士資格を取れなかったため、やむを得ず、親族や第三者の税理士資格を持つ人を後継者とした事務所の話もよく聞きます。
中には後継者の税理士資格取得が間に合わず、事務所を閉鎖しなければならなかった話も聞きます。
「後継者となり得る人がいて、その後継者に引き継ぐ意欲がある・・・でも資格がないので引き継げない。」
今回手紙を送ってきた税理士の事務所もこの様な状況だと思います。この手紙を読んでみて、改めて税理士事務所の事業承継の難しさを痛感したという話でした。